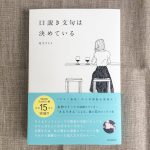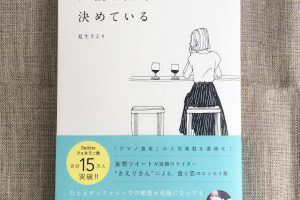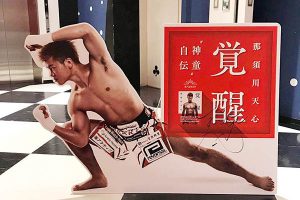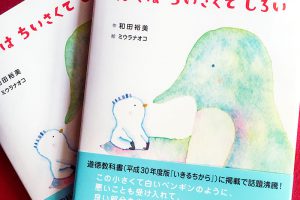前回は、ISBNコードとJANコード、そして、工夫次第で出版社で必要となる固定費はなくせることを紹介しました(なかなか編集費や営業費をレベニューシェアにできる組織は少ないと思いますが)。
今回は、出版事業で肝となる流通ルートについて書いていきます。
新規の取次口座取得は至難の業
全国には1万数千店の書店があり、一般的には取次と呼ばれる業者を通して、本は流通しています。
クラーケンはどちらかというとメジャー路線なので(たくさん刷ってたくさん売るタイプ)、当初は取次ルートを使う予定でした。
弊社(クラウドブックス)と一緒にクラーケンを立ち上げたホビーメーカー・ケンエレファントは、グッズの流通等でトーハンや日販と取引があり、スムーズに口座がつくれそうなムードがあったのです。
しかし、噂通りの条件の悪さにあ然とし(老舗の大手は翌月払い→新規は6ヵ月後払い&30%保留、老舗の大手は掛け率69%→新規は実質62%など)、別の方法を模索することになりました。
出版社の流通代行は使う意味なし
最初に検討したのはいくつかの出版社が行っている流通代行。何社かまわりましたが、正直、詐欺に近いところが多かったです。ノーリスクで10%くらい抜こうとするところがほとんどでした。
特にS社などは、歩戻しと呼ばれる配本手数料がかからないAmazonとの直取引に関しても、なぜか7%の手数料を契約書上で要求してきました(57%の64%戻し。S社はAmazonと67%契約なので、流通代行手数料を3%引いた上に歩戻しを7%取る計算)。
ちなみにクラーケンはAmazonとは直取引で、電子情報で連携している倉庫と契約することで、新規出版社ながら65%の特別掛率を実現しています(2017年6月末までの期間限定だったため、今後新たにこの掛率で契約できるかは不明です)。
倉庫側で自動で受注と補充が行われるため、手間もかかりません。これだけでも、流通代行を使うことの意味のなさは伝わるのではないでしょうか(アルファポリスと星雲社の関係がほぼ唯一の成功事例では。おそらく優遇されているのだと思いますが)。
公正でオープンなトランスビュー方式
最終的にクラーケンが契約したのが、直取引を代行しているトランスビューです。東浩紀さんの『ゲンロン』シリーズなどもいまはトランスビュー扱いなので、その存在を知っている方も多いかもしれません。
直取引契約済みの書店がすでに約2000店舗あり、その他の書店にも取次ルートで本を届けることが可能(後者は買切限定、返品不可)。
費用は公正そのもので、トランスビューの工藤さんに話をうかがって、本当にホッとしたのをよく覚えています。工藤さんがいなければ、クラーケンは空中分解していたかもしれません。
トランスビュー方式については、石橋毅史『まっ直ぐに本を売る』(苦楽堂)に詳しいので、気になる方はぜひ一読を(本としても面白く、クラーケンも4人中2人が購入しています)。単純に手数料何%という方式ではないので、なかなかここでは説明しづらいのです。
Amazonとはe託で直取引し、リアル書店は基本トランスビュー扱い。そして、書店以外での販売も模索していく。これが、クラーケンがたどり着いた新規出版社の流通ルートの最適解でした。
……次回へ続く。
執筆者

鈴木収春(すずき・かずはる)
クラウドブックス株式会社代表取締役/クラーケン編集長
1979年生まれ。講談社客員編集者を経て、出版エージェンシー・クラウドブックスを設立。ドミニック・ローホー『シンプルリスト』、須藤元気『今日が残りの人生最初の日』、関智一『声優に死す』などを担当。東京作家大学などで講師としても活動中。